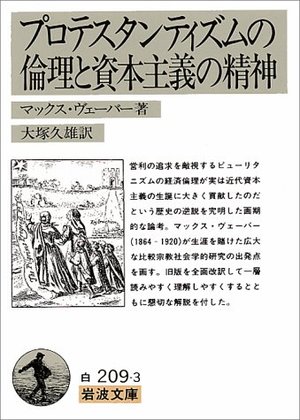プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神
著者
マックス・ヴェーバー(1864~1920)
ドイツの社会学者、経済学者。宗教生活と経済活動のかかわりを論じた『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で名高い。社会学方法論、政治社会学、都市社会学、法社会学などの研究でも大きな業績をあげ、その後の社会学の研究に大きな影響をあたえた。社会学黎明期のコントやスペンサーに続く社会学者として、エミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並び称される。
ドイツの社会学者、経済学者。宗教生活と経済活動のかかわりを論じた『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で名高い。社会学方法論、政治社会学、都市社会学、法社会学などの研究でも大きな業績をあげ、その後の社会学の研究に大きな影響をあたえた。社会学黎明期のコントやスペンサーに続く社会学者として、エミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並び称される。
本書の要点
- 要点1ドイツの諸地域において企業経営者や商工業者、上層の熟練労働者、技術者などの資本主義経済に適合した職業従事者の比率が、プロテスタントに多かった。
- 要点2カルヴィニズムの信徒たちは、禁欲的に職業労働に専念して神の栄光のために財産を増やすことによって、神から「選ばれた者」に属しているという「救いの確信」を獲得できると考え、それを実践したのである。
- 要点3こうした生活態度は、意図せずして合理的産業経営を基本とする社会的機構をつくりあげ、いつしか外的な社会機構が禁欲的行動を強制するようになった。すると、宗教的な信仰は力を失い、禁欲の精神自体が忘れられてしまった。
要約
問題
信仰と社会層分化

Teka77/iStock/Thinkstock
ヴェーバーは、ドイツの諸地域において企業経営者や商工業者、上層の熟練労働者などの資本主義経済に適合した職業従事者にかかわるプロテスタントの数が、相対的に多いという事実の指摘から議論をはじめる。カトリック信徒の職人は、手工業を続け、親方職人になる道を選ぶことが多いのに対し、プロテスタントの職人の多くは、工場経営の幹部や熟練労働者の上層になろうとする。それぞれの信徒の傾向は、支配的社会層と非支配的社会層のどちらに属していても変わらなかった。こうした現象は、プロテスタンティズムの宗教倫理のほうがカトリックのそれよりも資本主義的な経済合理主義により適しているからだとヴェーバーは説明する。プロテスタントの教会や信団(ゼクテ)などには共通して、熟達した資本主義的な事業感覚と、禁欲的な信仰が共存しているという事実も、その裏付けとなっている。
資本主義の精神
ヴェーバーは、中産的生産者層のなかから近代の産業資本家が成長してくる時期に、彼らの成長を内面から推し進めた「資本主義の精神」を説明するために、ベンジャミン・フランクリンの著書から、勤労や節約といった徳性を引用する。ひたむきな勤労態度や、労働能力を高める冷静な克己心や節制は、労働が絶対的な自己目的(天職)であるとして正当な利潤を追求させた。この精神は、プロテスタンティズムの宗教教育の結果として立ち現われたものだとヴェーバーは言う。
ヴェーバーは、こうした徳性を統一した行動システムにまでまとめあげ、社会に定着させたエートス(倫理的雰囲気)を「資本主義の精神」と呼んでいるのだ。
「天職」観念の萌芽
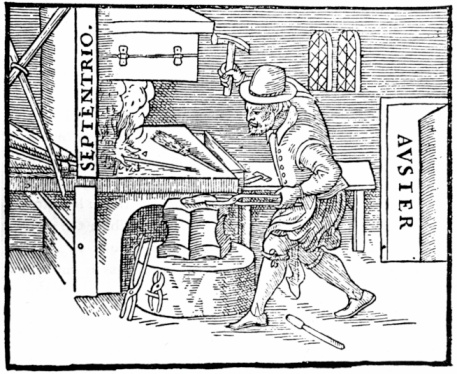
Photos.com/PHOTOS.com>>/Thinkstock
これまで説明した「資本主義の精神」の核となる「天職」という言葉は、宗教改革のときに行われたマルティン・ルッターの聖書翻訳に由来する。「Beruf(天職)」という観念は、世俗の職業は神の召命であり、神から与えられた義務を遂行することこそが神の意志にかなうという考え方である。それは、プロテスタントの優勢な諸民族に特有な思想として発達してきたものであることを、ヴェーバーは証明しようとしている。
中世においては、宗教的意義が認められている仕事は、世俗外に生きる聖職者の仕事のみだった。だが、世俗内の日常的労働に宗教的意義を持たせるようになったのが「天職」という言葉であり、観念であった。
しかしルッター自身は、あくまで世俗における労働を道徳的に重視しただけであり、「資本主義の精神」につながるような新たな見方を打ち出したわけではない。ルッターは、各人は神から与えられた職業と身分にとどまり、その枠を越えようとする努力をしてはいけないと考えており、彼自身は、人間生活にも神の摂理を強調する伝統主義的な思想から脱することはできなかった。
【必読ポイント!】 禁欲的プロテスタンティズムの天職倫理
世俗内的禁欲の宗教的基盤

Vladimir Arndt/iStock/Thinkstock
「天職」観念がもたらした影響をより詳しく探るため、ヴェーバーは、さまざまな形態のあるプロテスタンティズムのなかでも禁欲的なピュウリタニズムの宗教的基盤に着目する。禁欲的プロテスタンティズムは主に、17世紀に西ヨーロッパに広まったカルヴィニズム、敬虔派(パイエティズム)、メソジスト派、洗礼派運動から発生した諸信団(ゼクテ)の四つが担っていた。とりわけ、禁欲的プロテスタンティズムを独自の形で進めたのは、カルヴィニズムと洗礼派である。広義の「ピュウリタニズム」として考えられる上記の教義は互いに結合しあい、信徒たちの「道徳的生活態度」は非常に似ていた。
なかでも、カルヴィニズムを特徴づけている教義に、神に救われるかどうかはあらかじめ決まっているという「予定説」がある。

この続きを見るには...
残り1968/3486文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.07.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約