まちの本屋
知を編み、血を継ぎ、地を耕す
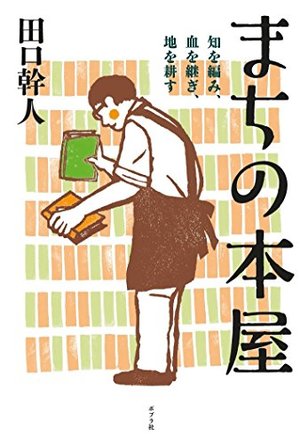
著者
田口 幹人(たぐち・みきと)
さわや書店フェザン店(岩手県盛岡)店長。1973年、岩手県西和賀町(旧・湯田町)の本屋の息子として生まれる。幼少時代から店頭に立ち、読みたい本を読み、小学生の頃にはレジ打ちや配達などもしていた。古本屋に入り浸る学生時代の後、盛岡の第一書店に就職。5年半の勤務を経て、実家のまりや書店を継ぐ。7年間の苦闘の末、店を閉じ、さわや書店に再就職。2011年より現職。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに、中学校での読書教育や、職場体験の中学生の受け入れ、イベントの企画、図書館と書店との協働など積極的に行う。「売る」と決めた本は、あらゆる工夫をして徹底的に売ることでも有名で、さわや書店から生まれたベストセラーは数多い。
さわや書店フェザン店(岩手県盛岡)店長。1973年、岩手県西和賀町(旧・湯田町)の本屋の息子として生まれる。幼少時代から店頭に立ち、読みたい本を読み、小学生の頃にはレジ打ちや配達などもしていた。古本屋に入り浸る学生時代の後、盛岡の第一書店に就職。5年半の勤務を経て、実家のまりや書店を継ぐ。7年間の苦闘の末、店を閉じ、さわや書店に再就職。2011年より現職。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに、中学校での読書教育や、職場体験の中学生の受け入れ、イベントの企画、図書館と書店との協働など積極的に行う。「売る」と決めた本は、あらゆる工夫をして徹底的に売ることでも有名で、さわや書店から生まれたベストセラーは数多い。
本書の要点
- 要点1本ごとに異なる「旬」のタイミングで、お客様にその本を提案できるかどうかが書店員の腕の見せどころである。
- 要点2本当に売れる本を生み出すには、お客様の導線を考え、お客様が本の魅力を最大限感じられる「出会い方」を想像することが大切である。
- 要点3著者がめざすのは、店頭も外商も含めた、本屋の「六次産業化」である。さわや書店は、「まちづくりへの参画」をテーマに、本を介して異業種と交流している。
要約
本屋との切っても切れない関係
まちの本屋をめざす原点
岩手県と秋田県の県境にある著者の実家は、本屋を切り盛りしていた。小学生だった著者が鮮烈に覚えているのが、コミュニティーの場としての本屋の姿である。著者は小学生からレジを打ち、本の配達もしていた。
大学時代には古本屋に足しげく通い、本の虫だった著者が就職を決めたのは、盛岡の第一書店という中規模の本屋だった。そこで任された最初の仕事は、入荷した本の仕分けと、売れ行きの芳しくない本を取次へ戻す返品である。当時、返品時にはすべて手書き伝票を書く必要があった。膨大な伝票を書く中で、著者は売れない本の理由を知ることができた。
書店員としての原点になったのは、さわや書店の名物店長、伊藤清彦氏との出会いだった。著者は彼から書店員としての矜持を学んだ。伊藤氏はこう語った。「本には旬がある。古い本でも旬がやってくる。そのタイミングでお客様に提案できるかが書店員には問われるのだ」。
目の前のお客様と本との出会いのきっかけを意図的につくることが大事な仕事なのである。例えば、TPPが話題になったとき、『農協』という本を展開すると、品切れになるほど売れていったという。また、一人の書店員が出会える本には限りがあるため、本屋の数だけ、書店員の数だけ、違う売り場が生まれるのである。
まちから本屋を消した過去

©iStock.com/takkemei
第一書店での5年半の勤務を経て、著者は実家の本屋を継いだ。人口減少に歯止めがかからない地域において、街の本屋は子どもたちのコミュニティーでもあり、年配者の安否確認の場でもあった。ところが、街の縮小とともに、売上や来客数が減少の一途をたどり、著者が本屋を継いで7年目、ついに店をたたむことになった。すべての棚から本がなくなるという、筆舌に尽くしがたい苦しみの中で、伊藤氏から「いつでもいいから、(さわや書店に)おいで」と声がかかった。

この続きを見るには...
残り3420/4202文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.01.27
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











