会社を立て直す仕事
不振企業を蘇らせるターンアラウンド
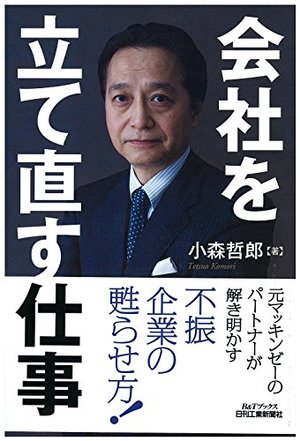
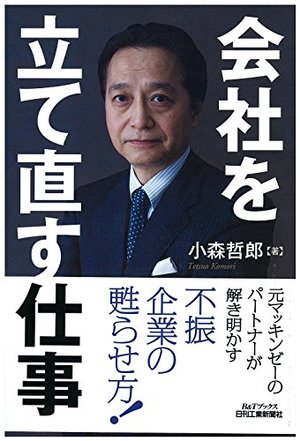
著者
小森 哲郎(こもり てつお)
昭和33年12月1日生、神奈川県出身。昭和59年3月 早稲田大学大学院 理工学研究科 生産工学修士課程修了、同年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社後、平成5年12月同社プリンシパル(パートナー)。平成14年6月(株)アスキー代表取締役社長CEOに就任。平成17年6月(株)巴川製紙所社外取締役就任(現任)。平成18年2月カネボウ株式会社(のちのクラシエホールディングス株式会社)取締役兼代表執行役社長CEOに就任。平成21年8月ユニゾン・キャピタル(株)マネジメントアドバイザー(現任)、平成24年6月旭テック株式会社社外取締役(現任)、平成27年3月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役就任(現任)。平成27年10月、(株)LIXILが自社の1事業部を「株式会社建デポ」として独立させ、その代表取締役社長CEOに就任(現任)。
昭和33年12月1日生、神奈川県出身。昭和59年3月 早稲田大学大学院 理工学研究科 生産工学修士課程修了、同年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社後、平成5年12月同社プリンシパル(パートナー)。平成14年6月(株)アスキー代表取締役社長CEOに就任。平成17年6月(株)巴川製紙所社外取締役就任(現任)。平成18年2月カネボウ株式会社(のちのクラシエホールディングス株式会社)取締役兼代表執行役社長CEOに就任。平成21年8月ユニゾン・キャピタル(株)マネジメントアドバイザー(現任)、平成24年6月旭テック株式会社社外取締役(現任)、平成27年3月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役就任(現任)。平成27年10月、(株)LIXILが自社の1事業部を「株式会社建デポ」として独立させ、その代表取締役社長CEOに就任(現任)。
本書の要点
- 要点1再生の鉄則は、「Shrink to Grow」であり、自社でコントロールしやすいコスト削減等の効率性向上による利益率改善から改革をスタートし、成長の原資を稼いだ上で売上成長に向けた施策に注力していくことだ。
- 要点2変革の成功のカギは、「危機感(変革のWhy)」「目標・方向感(変革のWhat)」「担い手(人に関するHow)」「一貫した施策(施策に関するHow)」の4つにある。
要約
水面下からの逆転経営 ターンアラウンド2つの事例
IT系ベンチャー出版社A社の場合

Avosb/iStock/Thinkstock
A社は、かつて著名だったIT関係のベンチャー出版社で、IT関連の雑誌や書籍出版を行っていた。著者が参画した当時は、出版業以外にも、不採算な事業を多く抱えているとともに、コア事業である出版業も赤字だった。非コア事業は、事業を支える強みや基盤を持っていないことから、売却等による撤退を進めていた。
IT関係の出版事業は、既にパソコンソフトの技術が汎用化したため市場縮小が進んでおり、競争状況としても各分野で業界3位あるいは4位という低い地位に甘んじていた。
出版社には編集が強くコンテンツで勝負する企業と、コンテンツ作成は編集プロダクションに外注して企画・営業が価値を出す企業に分かれる。A社は前者であり、編集オタク、パソコンオタクが多くいる企業で、最大のコスト項目は人件費であり、固定費がコスト全体の6割を占めた。収益面で見ると、大黒柱の製品があり、全体の売上の3割、利益の6割を稼いでいた。そして、創業時からの同好会的な雰囲気を持ち、こだわりを持って皆よく働く一方で、事業を運営するという観点ではマネジメント力が不足していた。
A社を復活に導いた変革プログラム
事業再生の1年目の施策は、自らコントロールしやすいコスト面を中心に行い、その後新製品投入による成長施策に移行していくという流れとした。体制面では、「戦略会議」という課題解決の会議体を設置、更にターンアラウンド・マネジャの能力増幅機能となる「戦略企画部門」を設置した。それに加え、著者自ら「全社員への個別インタビュー」を行った。
特に、ブラックボックスになっていた出版社のオペレーションについて、1人当たり1時間をかけたインタビューを定例プログラム化し、2年間で350人ほどが対象となった。
A社固有の仕組みで「ベスト・プラクティス」の1つとなったのは、「書籍の売上・収益管理システム」である。出版業界の特徴として、単行本などの書籍は当たり外れが大きい。書店へ配本後、売れずに返本となるケースも多い一方で、地道な販促が効果を上げ、売上が伸びるケースもある。この効率の悪さを挽回するため、編集者は手掛ける製品数を増大させようとするが、作ったら作りっぱなしで、収益の検証もできていなかった。
そのため、企画書段階、マーケティング計画段階と比べ、このまま推移すると売上・原価の双方で、どのような差異が生じるかがわかる「シミュレーション・モデル」を創り上げたのだ。得られる情報を編集者本人にもフィードバックする仕組みも整え、稼げる編集者を可視化して、生産性を高める方向にドライブすることができた。
取り組みの結果、2年間で営業利益率がマイナス5%からプラス13%にも回復し、課題解決ガバナンスの土台も整備され、自律的に動くようになったのだ。
日本経済の成長とともに拡大した伝統あるメーカーB社の場合

nd3000/iStock/Thinkstock
B社は、明治初期に創業した紡績業を母体とし、様々な事業分野へと業容が拡大し、一時期輸出企業として日本一の規模を誇っていた。しかし、過度な多角化と経営改革の遅れ等により業績が低迷し、産業再生機構の管理下となった。

この続きを見るには...
残り3147/4458文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.03.23
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











