PDCAの本質
PDCAから得られるもの

もともとPDCAは、製造工程の不具合、品質改善に取り組んできた米国のウォルター・シューハート博士が提唱した考え方がベースとなっている。製造業におけるエンジニアリングのアプローチから生まれたPDCAの方法論は、個人にとどまらず、組織においても正しく経験値を重ね、その実践力を高めるためのものとなる。
PDCAを廻すということは、結果の検証(C)をおこない次の企画(P)に反映させるべき、学びのポイントを明確にすること。そしてよく考えて企画(P)し、精度高く実行(D)して、改善・進化(A)させることである。PDCAを廻す中で、たとえ失敗したとしても結果の検証(C)を行っているかぎり、場数を踏むたびに経験則が蓄積されて、やがて「自信」にあふれる状態が実現するのである。難易度の高い問題にも的確な判断ができるようになり、さらに、経験則から先を見通す能力をも得ることができ、「次に何がおこるか」をロジカルに説明することも可能となる。
PDCAが廻っていない企業で起きること
経営視点でのPDCAが廻っていない企業では、経営者が社内の実態を把握することが難しくなる。よって経営判断をするにあたり、十分な情報がなく、筋の通った議論もできずに、経営者が「自信」をもてない状況となる。こうした経営者は現状維持を目的とした、組織の和を優先させて、イニシアティブをとらない傾向が強くなる。
さらに「自信」のないマネジメントは個人的な思惑のつけ入る隙をつくり、社内に保身文化を生むことになる。競合企業の真似のみを行う、横並び感覚が横行し、改革への芽が出たとしても「うちの文化と違うから」と摘んでしまうこともある。
このような状況を回避してPDCAを推進するのに欠かせない要素は、優良企業をつくりあげるという「パッション」すなわち、情熱、意思、想いである。
物事の成否は、理論上の正しさもさることながら、「自分にはできる」「自社ならば、なんとかなる」といった「自信」をもって企画と実践に臨めるにかにかかってくる。「自信」を培うためには、正しく場数を踏む、つまりPDCAを廻すという、事業運営を通じての学習が必要となる。「パッション」と「自信」はPDCAを通じて、双方が高められていくものといえる。
優良企業の実践力
「戦略」と「実践力」
業績不振に悩む企業のトップが経営コンサルタントに相談するのは「現状を打破する戦略がほしい」という内容が多い。「戦略」は合理的に組み立てられた賢明なシナリオではあるものの、あくまで成長のための初期仮説である。








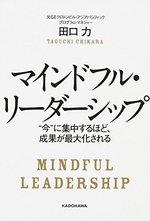











![イシューからはじめよ[改訂版]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F18_cover_150.jpg&w=3840&q=75)