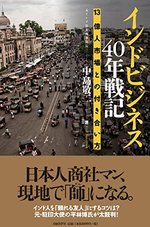決定版 これがガバナンス経営だ!
ストーリーで学ぶ企業統治のリアル

著者
冨山 和彦(とやま かずひこ)
経営共創基盤(IGPI)代表取締役CEO
ボストン コンサルティング グループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、IGPIを設立。オムロン社外取締役、ぴあ社外取締役、経済同友会副代表幹事。財務省財政制度等審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会委員、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会委員他。
澤 陽男
経営共創基盤(IGPI)ディレクター
西村あさひ法律事務所にて、事業再生を専門とし、多岐にわたる業種について、法的・私的整理手続を支援する他、一般企業法務、M&A等に従事。IGPI参画後は、通信業を中心に新規事業開発のハンズオン支援等やファイナンシャルアドバイザリー業務等に携わる他、経済同友会に出向、コーポレートガバナンスや成長戦略等に関する政策提言やその実現に向けた活動に従事。特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会委員。青山学院大学法学部卒業。弁護士。
経営共創基盤(IGPI)代表取締役CEO
ボストン コンサルティング グループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、IGPIを設立。オムロン社外取締役、ぴあ社外取締役、経済同友会副代表幹事。財務省財政制度等審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会委員、金融庁スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員、経済産業省産業構造審議会新産業構造部会委員他。
澤 陽男
経営共創基盤(IGPI)ディレクター
西村あさひ法律事務所にて、事業再生を専門とし、多岐にわたる業種について、法的・私的整理手続を支援する他、一般企業法務、M&A等に従事。IGPI参画後は、通信業を中心に新規事業開発のハンズオン支援等やファイナンシャルアドバイザリー業務等に携わる他、経済同友会に出向、コーポレートガバナンスや成長戦略等に関する政策提言やその実現に向けた活動に従事。特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会委員。青山学院大学法学部卒業。弁護士。
本書の要点
- 要点1「稼ぐ力」が衰えてきている今の日本には「攻めのガバナンス」が必要であり、「ステークホルダー主義に立脚したエクイティーガバナンス」をめざすべきである。
- 要点2コーポレートガバナンスの基本は、根本規範である会社法に基づきながら株主に選任された経営陣が健全な会社経営を行い、監査役がその適法性を監査・監督することである。
- 要点3取締役会の在り方がガバナンス改革における中心的な課題である。そして時代の潮流は社内取締役から社外取締役に変わってきており、昨今「世の中目線のモニタリング機能」がますます求められている。
要約
なぜ今ガバナンス経営なのか
「失われた20年」の理由

Yuriy Panyukov/Hemera/Thinkstock
過去20年にわたり、日本の上場大企業は世界での地位を失ってきた。売上然り、利益創出力然り、時価総額然り。またそれによって国内での雇用シェアも失い、雇用が年々海外へと流出してしまった。こうした事態への説明として一般的に言われるのは新興国の勃興だが、それは正しくない。フォーチュン誌が年一回発表している各種指標「フォーチュン・グローバル500」で日本企業は20年前の3分の1ほどに減ったが、欧米企業は1~2割ほどしか減少していない。先進国では完全に日本の一人負けなのである。
では日本の企業が力を失ってきた本当の理由は何か。それはひとえにROS(売上高利益率)の低下、すなわち本業における企業競争力の低下である。長年、数々の企業再生に関わってきた著者によると、日本の技術力や現場力は今もって衰えてはいないという。むしろ世界的に非常に高く評価されている。それにも関わらず企業が力を失ってきたのは、企業経営に問題があるからであり、企業経営者とコーポレートガバナンスが機能不全を起こしているからである。企業ガバナンスが変われば日本も変わる。日本経済が再び活力を取り戻すために、今こそガバナンス経営を実践することが求められているのだ。
時代はコーポレートガバナンスへ

pichet_w/iStock/Thinkstock
2012年12月に第2次安倍政権が発足すると、経済再興政策としてアベノミクスが打ち出されたのは誰もが知るところである。2013年6月に公表された最初の計画では、コーポレートガバナンスは無数の政策の1項目に過ぎなかったが、翌2014年に発表された改訂版では「コーポレートガバナンスの強化」が最重要施策とされた。さらに翌2015年に出された改訂版でも、「コーポレートガバナンスの更なる強化」が、引き続き最優先課題として掲げられたのである。そして事実、この時期に日本のコーポレートガバナンスは大きく変革した。
では具体的にどのような改革がなされてきたのだろうか。一連の改革のスタートは、2014年1月に始まった東証におけるJPX日経インデックス400の公表からだった。これは、東証上場企業3400社から投資家にとって魅力の高い銘柄400社を選んで発表するもので、ROEなどのほかに独立社外取締役を設置しているかなどのガバナンス体制も考慮される。この新たな制度導入により、選出されなかったことを恥じた企業がガバナンス体制を整える方向へ作用していったのである。
続いて2014年2月には、金融庁にてスチュワードシップ・コードが制定された。スチュワードシップ・コードには、機関投資家が資金提供者の中長期的なリターンを拡大するために、投資先企業をガバナンスする責任を負っていることが明記されている。そしてさらに同年6月には会社法の改正案が成立した。中でも注目されたのが「社外取締役を実質義務付けする」改正で、安倍政権の強いイニシアチブによって実現された。
政策・制度レベルでこのような改革が行われてきた背景には、先に述べたような日本企業の凋落がある。日本企業と欧米企業の売上高利益率を比較してみると、日本が4%前後であるのに対し欧米は10%前後と大きな開きがある。つまり本業で競争力を失っている、稼ぐ力のない企業は、将来に向けたR&D投資や設備投資、M&A投資、人材投資など、持続的な成長に向けたあらゆる投資をできなくなり、その結果持続的な成長力も失っていくのは当然である。特に人材投資をしなかった罪は大きく、すでに雇った正社員サラリーマンを守ることに全力を注いできた日本企業は、いつしか「正社員サラリーマンのサラリーマンによるサラリーマンのための経営(=サラリーマン共同体至上主義)」に陥ってしまったのである。こうしたステークホルダー主義からかけ離れた日本的経営から脱するためにも、コーポレートガバナンスの実践が希求されている。
【必読ポイント!】 ガバナンス経営実践のために
日本がめざすべきコーポレートガバナンスの在り方

designer491/iStock/Thinkstock
日本では長らく、サラリーマン中心主義に基づいてコーポレートガバナンスが行われてきた。それはつまり、長きにわたってサラリーマンの特権の保護を最優先する一方で、株主などの外部の声に重きを置かないガバナンスを行ってきたということだ。最近では徐々に変わりつつあるものの、少し前まで日本企業の取締役会はその会社の生え抜きサラリーマン出身の取締役で構成されていた。そのため、諸外国では独立社外取締役を導入することが主流になっている中、日本では1名の独立社外取締役を置くか置かないかで大騒ぎしてきた。

この続きを見るには...
残り2217/4112文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.09.12
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約