インドビジネス40年戦記
13億人市場との付き合い方
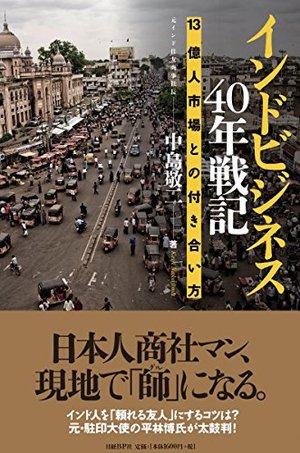
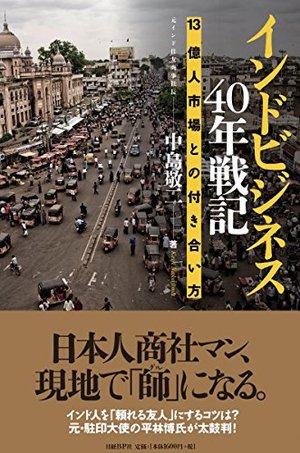
著者
中島 敬二(なかじま けいじ)
元インド住友商事社長。Nakajima Consultancy Services社長。インド在住。1994年山梨県生まれ。1968年に慶應義塾大学経済学部を卒業し、住友商事入社。1974年からインドとの取引にかかわり、スズキがインドに設立した合併会社マルチには立ち上げ時期からかかわる。1998年からインド住友商事社長。デリー日本人学校理事長、デリー商工会議所会長などを歴任。2001年本社に帰任し、理事・広報部長。2004年に定年退職後、関連会社社長に就任したが、住友商事が出資するインド企業の再建を依頼され、同社Directorとして2006年から3度目のインド赴任。退任後、DMICインド政府アドバイザー(日本政府派遣)、ハリヤナ州政府名誉顧問などを務める。その後インドで起業し、日本企業のインド進出を支援するコンサルタント会社、日本食レストラン、ホテルなどを経営する。
元インド住友商事社長。Nakajima Consultancy Services社長。インド在住。1994年山梨県生まれ。1968年に慶應義塾大学経済学部を卒業し、住友商事入社。1974年からインドとの取引にかかわり、スズキがインドに設立した合併会社マルチには立ち上げ時期からかかわる。1998年からインド住友商事社長。デリー日本人学校理事長、デリー商工会議所会長などを歴任。2001年本社に帰任し、理事・広報部長。2004年に定年退職後、関連会社社長に就任したが、住友商事が出資するインド企業の再建を依頼され、同社Directorとして2006年から3度目のインド赴任。退任後、DMICインド政府アドバイザー(日本政府派遣)、ハリヤナ州政府名誉顧問などを務める。その後インドで起業し、日本企業のインド進出を支援するコンサルタント会社、日本食レストラン、ホテルなどを経営する。
本書の要点
- 要点1著者はもともとインド嫌いの人間であったが、経験を重ねていくなかでインド人とのつきあい方を学んでいき、定年後もインドで新規事業を立ち上げるなど、今では立派な「インド大好き人間」になった。
- 要点2日本とインドの考え方は大きく異なっているため、いたずらに比較するのではなく、「そのような文化もある」と受け入れる心を持つのが肝心である。
- 要点3インドには「ジェガード」という、「先のことなどわからないのに計画を立てるのは無駄であり、応急処置的な対応を心がけたほうがいい」という独特な考え方があると知っておくべきである。
要約
あるインド市場開拓者の軌跡
はじめは「インド嫌い人間」だった

Meinzahn/iStock/Thinkstock
のちに40年以上の長きにわたってインドと関わることになる著者が、商社のインド担当になったのは全くの偶然であった。入社して数年が経ったある日、近くにいた同僚がインド赴任を命じられた。しかし、その同僚は辞める覚悟まで示してその命令をかたくなに拒否した。その時、当惑する上司と目があったのが著者であった。その瞬間、否応なく著者のインド赴任が決まった。そして、それから定年以降まで続く、インドとの付き合いが始まったのである。
当時、著者のインドへのイメージはひどいものであった。衛生状態が劣悪で、下痢は当たり前、赤痢やコレラの危険性もある危険な国。お金もなく、あらゆる仕事に政府の規制がおよび、ダーティーな取引も横行し、ビジネスが極度に難しい国。こうした印象を持っていた著者は、インド赴任に対してどうしても乗り気にはなれなかった。
実際、赴任してはじめの頃は、インド人の文化や慣習にとまどうことばかりであった。根強いカースト制度、信じられないほどの粘り強さでの価格交渉、確固たるプライド――これらを見せつけられる場面に次々遭遇した。しかし、経験を重ねていくなかで、徐々にインド人との付き合い方を学んでいったのである。
新規案件での大きな成功
それでもインドへの苦手意識は簡単には消えなかった。インドの担当を外れてメキシコ駐在となる内示を受けたとき、妻と祝杯をあげたほどである。メキシコへの駐在は5年ほど続き、その後、本社の自動車部へ課長として異動となった。
しかし、当時の自動車部はアメリカとの取引が大半を占めており、自動車の知識もなく、英語もできない著者は思い悩んだ。そこで、自分にできることをしようと考えた結果、インドでのビジネスに活路を見出すことにしたのである。
久しぶりのインド出張が決まった著者は、インド大手グループの傘下企業である自動車部品メーカーの幹部が、日本企業との提携交渉のために来日する予定だという情報をつかんだ。その交渉の仲介人に起用してもらうため、著者はアポイントメントなしで、その自動車部品メーカーを訪問した。受付からの質問をうまくかわし、ゼネラルマネージャーの冷たい対応にも屈せず、なんとかキーマンである副社長との面会にこぎつけた。
副社長は軍人のようなたたずまいの人物であった。客人を席に案内したあと、何も言わずに向かい合って座り、黙ってこちらを見ていた。著者は頭が真っ白になったが、失うものなど何もないと考え、英語が苦手であることも忘れてとにかく話し続けた。著者が話し終わった後、副社長は腕を組みながら、眼をじっとつぶっていた。諦めの気持ちが湧いてきた著者が、いよいよ席を立とうとしたその時、副社長はゆっくり言った。「貴方を信じよう。貴方の会社を通じて話を進めることに同意する」と。もちろん、これまでインド人との付き合いを学んできた著者は、確認の文書を求めることを忘れなかった。
赴任時代の出来事

PsychoShadowMaker/iStock/Thinkstock
自動車部に異動となってから7年が経過したとき、インド赴任の辞令がでた。長女が大学受験を翌年に控え、次女は高校1年生だったため、単身赴任をせざるをえないと著者は考えていた。だが、妻と高校生になった娘が一緒に移り住むことに同意してくれた。
娘は英語が苦手であったが、現地のアメリカンスクールに苦労しながらも通いつづけた。著者も仕事が終わると急いで帰宅し、娘の勉強に付き合った。その甲斐があったのか、娘は最終的に、学校一の劣等生の状態から、最優秀学業生徒に選ばれるほどに実力をつけた。日本では家族との時間をあまり取れなかった著者だったが、インドでの駐在生活は結果的に、家族との絆を強固なものにした。
5年の任期を終え、部長として本社へ戻った後、1998年にインド住友商事の社長として、再度のインド赴任が言い渡された。

この続きを見るには...
残り2515/4099文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.09.15
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











