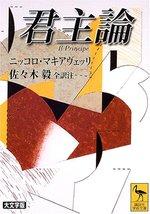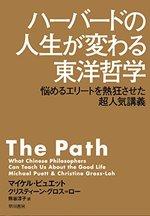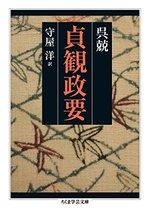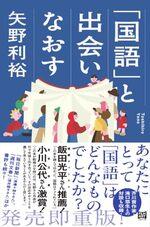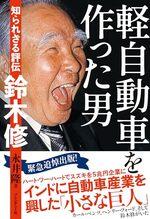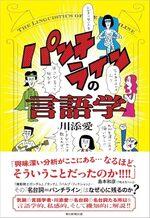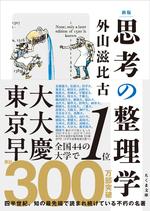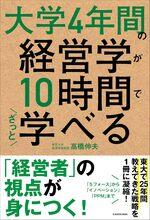『歎異抄』の見取り図――校注者「解題」より
『歎異抄』とは何か
まずは、本書に収録されている金子の「解題」を、以下に簡単にまとめてみたい。
『歎異抄』は、親鸞の語録をもとにしつつ、親鸞の死後に現れた様々な異説を歎き、親鸞の真意を伝えることを目的としている。著者は直弟子の唯円(ゆいえん)ということが、現在では定説になっている。親鸞の思想を伝える本は他にも覚如の『執持鈔』(しゅうじしょう)や『口伝鈔』(くでんしょう)があるが、これらは親鸞の孫である如信から伝え聞いたものと考えられるため、直接親鸞から聞いた話を記録したのは、この『歎異抄』だけといえる。
『歎異抄』の構成は二部に分かれており、前半部分は親鸞の言葉を集めたもの、後半部分は唯円が異説を批判する内容となっている。この親鸞の語録と唯円の歎異の内容は互いに対応しているが、とりわけ重要なのが第1章と第11章の対応だ。第1章は親鸞の信念を全体的に述べたもの、第11章は唯円の歎異の総論ともいえる箇所である。真宗の要旨を知りたければ、まずはこの部分を読み込むべきである、と金子は示唆している。
真宗の教義

「他力本願のむねをあかせるもろもろの聖教(教)は、本願を信じ(信)念仏をまうさば(行)仏になる(証)、そのほか、なにの学問かは往生の要なるべきや」と『歎異抄』のなかにあるように、真宗の中心的な教義はいたってシンプルだ。つまり、親鸞は、本願を信じるとは真実を心から受け入れるということであり、念仏はその道理を身につけるために行われるものだという。
では本願とは何か? 金子は、それは生死や愛憎の悩みを抱える生きとし生けるものを、苦しみのない場所に連れて行きたいという、無限の存在である如来の願いである、と解説する。人間は生まれながらにして不安や苦しみを背負っている。その人間に対し、如来は、老少善悪にかかわらず平等に慈悲のこころを持っている。そう考えることが「本願を信ずる」ということである。
『歎異抄』の価値と歎異の本質
この書の持つ大きな価値は、複雑に感じられる記述が一切ないこともそうだが、なにより親鸞個人の心境に焦点を当てて書かれていることだ。これが教義を説いた親鸞の主著『教行信証』(きょうぎょうしんしょう)との大きな違いであり、だからこそ長らく人々に親しまれてきたといえる。しかしそれは『歎異抄』が単純なだけの書物であることを意味しない。金子は「故に『教行信証』を背景として『歎異抄』を見れば、前者の教義はすべて後者の言葉の上に全現している。そしてそれが翻って後者の簡明な言葉が前者の広汎な教義を見開く眼となるのである」と評している。『教行信証』にある普遍の真実は、この書に著されているような個人としての親鸞の在りように深く根ざしているのである。
一方、親鸞の教えを伝えた唯円にとって、教えに背く行いと思われたのは、教えそのものを知識化することだった。「本願を信ずる」ことと「念仏をまうす」ことは同時に行われるものだ。『歎異抄』には、それぞれを別のものとして扱い、その片方を軽視したり、学問によって本願を理解しようとしたりする異説に対する歎きが込められている。ただ、それ以上に、唯円を執筆に向かわせた歎きとは、そもそもの現実の自分に立ち返って如来の恩徳を思うのでなければ、かえって救いの道が閉ざされてしまうことへの歎きにある。その心情を慮ってこそ、この書を理解することができるだろう、と金子は述べている。
【必読ポイント!】親鸞かく語りき
すべては念仏である

『歎異抄』第1章には、次のような親鸞の言葉がある。弥陀に助けられて極楽往生すると信じ、念仏がしたいという気持ちが心の中に生まれるとき、私たちの心の中は信心の喜びで満たされ、限りない恩恵を受けるようになる。弥陀が持つ救済の願いは万人に向けられている。