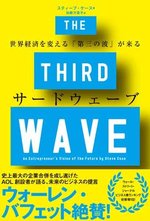ビジネスモデル総論
ビジネスモデルは「儲けの仕組み」
そもそも、ビジネスモデルの定義とは何か。ビジネスモデルとは、実質的な競争空間としての、ある業界を前提とした競争優位獲得を目的に設計・構築される仕組みを指す。また、その優位性は、持続可能なものであることはもちろん、競合が模倣できないものや、模倣されても優位性を保てるものであることが前提となる。大事なのは、ビジネスモデルが「儲けの仕組み」であることから、規則性や再現性と必要とするという点だ。
従来の戦略論は次の2種類である。1つ目は、ポーターたちが論じた、収益性が高い市場を探し、どの市場で戦うかという位置取りを選択する「ポジショニング学派」である。そして2つ目は、バーニーなどが唱えた、自社の資産や能力を重視して市場を選択する「ケイパビリティ学派」だ。いずれも市場の選択をテーマとしており、選んだ後に市場内部でどうすれば勝てるかという方策にはふれていない。一方、ビジネスモデルは業界内の戦い方を問題とし、これが今後の事業の成否を決する要素として考えられている。
なぜ今、ビジネスモデルが重要なのか?

これまでビジネスの現場では、市場内部における競争方法についての議論が抜け落ちていた。しかし、今ではビジネスモデルが重要視され始めている。現場のリーダーたちに、与えられた市場の中で競合に打ち勝つための指針が必要とされているからだ。
日本企業は、製品力による勝負を得意としてきた。しかし、模倣の横行やデジタル化、モジュール化が進む現在、世界の企業と互角に戦うには、製品力以外の強みが欠かせない。実際、ユニクロやネスレの躍進の背景には、ビジネスモデルの力がある。ビジネスモデルは、競争をリセットする大きな力を持つ。そのため、IoTやビッグデータによりビジネスモデルの変革がしやすくなった現在、業界下位に位置する企業や新規参入者にとっては大きなチャンスとなっている。そこで、ビジネスモデルへの感受性を磨くことこそが競争優位を獲得するカギとなる。
【必読ポイント!】 各論① 事業の内部モジュール編
アズ・ア・サービス
ビジネスモデルを考えるうえで、事業自体が持つ仕組みに着目したとき、顧客や提供価値を決める「対象市場定義」が必要となる。その一種である「アズ・ア・サービス」とは、主に製造業が製品の販売から、その製品機能の「サービスとしての提供」へと提供価値を変更するビジネスモデルを指す。
その最先端は富士ゼロックスやリコーなどの複写機業界である。コピー機を売るのではなく、コピー機の所有権をメーカーや代理店に留保し、コピー枚数に応じた課金にすることで、コピー機能を提供する。これにより、顧客はメンテナンスから解放され、モノの寿命が延長できると同時に、企業側は競合との価格競争から離脱し、メンテナンスのニーズを確実に獲得して顧客を囲い込むことができる。
「アズ・ア・サービス」の優位性は、いったんサービスを提供すれば、顧客の使用状況を把握でき、更新時のスイッチングリスクを減らせる点である。例えばICTのクラウドサービスでは、顧客のデータを管理するため、データ移行の費用や手間が顧客にとってスイッチの障壁になる。ただし、「アズ・ア・サービス」には、顧客との継続的な関係を築けるという利点があるものの、一度きりの取引では発生しなかった顧客マネジメントが必要になる。
事業間顧客流入

「事業間顧客流入」とは、ある先行事業で集客した顧客を、他の後続事業に結びつけ、後続事業の売上と利益の増大を図るビジネスモデルである。例えば、JR東日本は、鉄道事業の集客力を、ルミネなどの小売り事業やアトレなどのモール運営事業の集客に活用している。また、総合リース企業のオリックスは、小規模事業者向け会計ソフトでシェアが高い弥生を買収することで、その顧客基盤を自社サービスに活用しようとしているという。
先行する事業は高い集客力が前提となるため、公共性が高い事業や、利用開始の敷居が低い事業が望ましい。一方、後続する事業は提供価値の差別化をしづらい事業や、取引開始の敷居が高い事業であることが一般的だ。
このビジネスモデルの優位性の源泉は、