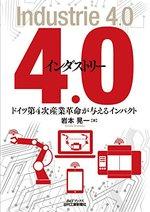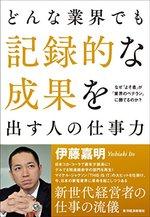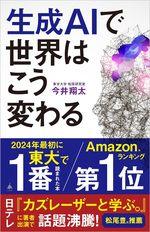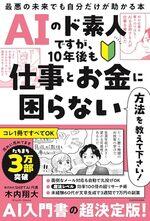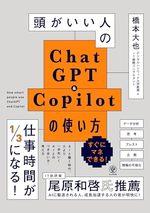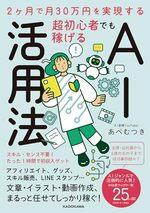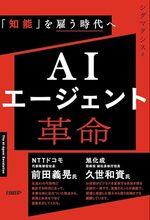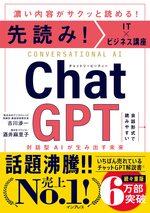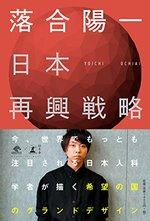【必読ポイント!】 「人工知能」は人間を超えるか?
人工知能とは何か
人工知能とはコンピューターのプログラムのことだが、従来型のプログラムとの最大の違いは、状況に応じてふるまいを変えることができるという点である。もともと日本では、1980年代から情報の内容によって処理形態を変えるような人工知能の研究が進んでいたが、当時は処理の元となるデータが不十分だった。しかし近年ウェブの広がりにより、膨大なデータを取得し、処理することが可能になった。これまでは「もし〇〇ならば××せよ」というようにルールを大量に定義してやる必要があったが、ビッグデータを読み込んで、自分自身でルールを学習することができるようになったのである。それにより、人工知能は加速度的に賢さを増している。
人工知能の「怖さ」の正体

もともとは人間を超えようと始まった人工知能の研究だが、想像以上に人間の知能は優れており、超えることは困難だとわかってきた。そのため現在では、人間よりも賢い知能の実現を目指そうとする「強いAI」派と、普通のコンピューターより少し知的な仕組みを作ろうとする「弱いAI」派の2つの流派に分かれて研究が進んでいる。
「強いAI」が実現すれば、やがて人間より賢い人工知能が生まれ、人間の仕事は奪われてしまうかもしれない。もしも人工知能が、自身より少しだけ賢い人工知能をつくり出すことができるなら、無限に賢い人工知能が瞬く間に誕生する。一説には、2045年にはコンピューターは人間を超え、開発と進化の主役となる「技術的特異点」(シンギュラリティ)が訪れるともいわれている。
人工知能が人間を超える可能性に対し、塩野は危機感を抱いているが、松尾は楽観的である。現状、経験から学習する能力や、それを次世代に受け継ぐ力は人間のほうがはるかに勝っているし、人間を支配するようにプログラミングされた人工知能をつくることは非常に難しいからだ。
松尾はむしろ、人工知能の予測精度の高まりに対して恐怖心を示している。人工知能は、ビッグデータの中から人間には発見できないようなパターンを見つけ出せるし、見つけ出した事実をそのまま認識してアクションを起こすことができる。
一方人間は、原因と結果がわかりやすい「因果関係」にとらわれがちである。たとえば、「おむつとビールがなぜか一緒に売れる」という現象があったとき、人工知能はためらいなく両者を並べて売ることができるが、人間は「若いお父さんが一緒に買っている」というような解釈をして納得しないとアクションを起こせない。松尾は、社会を変えるような人工知能は、人間のようにふるまうものではなく、ただただ予測精度の高い「箱」のようなものになるだろうと予想している。</p>