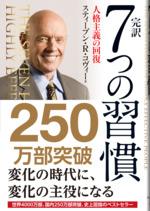アイデアをかたちにする
「おもしろい」を重視するプロジェクト制
ほぼ日のプロジェクトは、誰かが「これをやりたい」と思ったときに始まる。そこから他の社員に相談し、糸井重里氏へと相談。周囲から同意が得られると、正式なプロジェクトとなる。チームメンバーは社員同士の声がけで決まる。企画書や進捗報告も必要ない。
重視しているのは、あくまで発案者や周囲がそれを「おもしろい」と思っているかどうかだ。おもしろいと考えた要素を、深く考えたり探ったりすることに力を注ぐのである。
ほぼ日手帳も、ある社員が「ほぼ日読者の生徒手帳をつくろう」と言い出したことがきっかけで生まれた。そこからチームで話し合ってアイデアを出し、印刷や製本のプロと相談しながら、実際に手帳をつくっていった。
「マーケティング」は必要か

ほぼ日手帳の作成にあたっては、一般的なマーケティングはおこなわなかった。その代わりに、じぶんがお客さんになったら本当によろこぶかどうかを考え、「これは売れるに決まっている!」というところまでもっていくことを繰り返した。実際に手帳ができてからも、お客さん自身が手帳の使い方を発見することで、さらなる魅力が生まれていった。
当初は「ほぼ日」の中だけで販売していたほぼ日手帳だったが、あるとき社員が「ロフトで売れたらいいな」と言い出し、ロフトの公募制度に申し込むことになった。いざロフトでの取り扱いが始まると、売り場でお客さんが一緒にいた友人にほぼ日手帳の魅力を熱く語り、「営業」してくれた場面に出くわしたこともある。ほぼ日に営業はいない。だがお客さんも含め、みんなで営業するのがほぼ日なのかもしれないと糸井氏は語る。
人のよろこびを追求する
暮らしにかかわるあらゆるものが、ほぼ日の事業対象だ。期間限定の商店街のようなリアルイベント「生活のたのしみ展」は、「人間の生きる総体を見せたい」、「世界のどこにもない雑貨の見本市をやりたい」という思いからスタートした。雑貨を買うことは、生活を楽しむことにつながる。買いものはじぶんのポテンシャルの表現であり、自由のシンボルでもあるからだ。
会場ではお客さんたちが、ただサービスを受けるだけではなく、「つくり手」として「じぶんにもなにかできるか」と考えてくれて、「じぶんが役に立っている」というよろこびが双方向で生まれた。
【必読ポイント!】 ほぼ日の働き方改革
労働時間を減らして給料のベースを「上げる」

ほぼ日の「働き方改革」は、労働時間を減らしながら給料のベースを「上げる」というものだった。多くの会社は「集中して生産性を高めよう」と考える。しかし糸井氏は、この「集中」の定義について疑問を抱いている。生産性が上がるということは、質のいいアイデアをたくさん生み出すということだ。ならば勤務時間が減ったとしても、いいアイデアさえ生まれれば、それが新たな事業となり、利益を生み出すはずである。
「漫然と働く時間はもったいない」と感じた糸井氏は、社員に刺激を与えたいという気持ちから、一日の労働時間を一時間減らすことに決めた。加えて「ひとりで考える時間がアイデアを生む」と考え、打ち合わせなどの予定を入れず、会社に来なくてもいい「インディペンデントデー」も設けている。アイデアが生まれやすい環境をつくることが、ほぼ日の働き方改革なのだ。
「いい人」を募集する
人事採用の際は、採用告知そのものを「ほぼ日」の記事とし、「いい人募集」と呼びかけた。