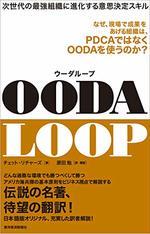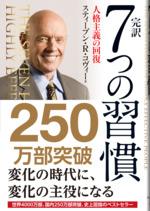【必読ポイント!】 両利きの経営
イノベーションとはリーダーシップである
成功している企業が変化を前にして革新を求められたとき、なぜこれほど適応しづらいのだろうか。著者らは、研究者として、またコンサルタントとして、多くの組織やリーダーたちと交流を重ねてきた。多くの企業は、戦略的なビジョンを掲げ、巨大な資本を持ち、優秀な人材を揃えている。ところが、そうした企業がイノベーションや変化に直面したとき、それに適応できず、目も当てられないほど凋落してしまうケースもある。それはなぜなのか。
著者らの結論は「リーダーシップ」の問題だということだ。問われているのは、変化に直面したときにリーダーがどう行動するかである。
本書の目的は、そうしたリーダーに「両利きの経営(ambidexterity)」という武器を提供することにある。両利きとは、左右の両手がどちらも利き手であるかのように自在に使えることを意味する。企業経営においては、既存の事業を深めていく「深化(exploitation)」と、新しい事業の開拓をめざす「探索(exploration)」の活動が、高い次元で両立している状態を指す。これが企業の継続的なイノベーションと、サバイバルを可能とする。
サクセストラップに陥らないために

しかし、企業にとって深化と探索のバランスをとるのは難しい。短期的な成功を保証するのは深化である。深化があるからこそ、企業は安定して質の高い製品・サービスを世に出し、社会的な信用を得られる。探索はそもそも非効率的で、リスクが高い。しかし、探索に取り組まない企業は、変化に直面したときに破綻する可能性が高いのも事実だ。
ある経営学者は次のように予言している。「老舗企業は常に深化に専念し、すでに知っていることの活用にかけては腕を上げていく。それで短期的に優勢になるが、徐々に力を失い、つぶれてしまう」。
このように、成功すればするほど深化に偏り、長期的に失敗の危険性が増してしまう。これを「サクセストラップ」という。著者らは、この罠に落ちた例としてコダックを、この罠から免れた例として富士フイルムを挙げている。サクセストラップから企業を救うのが、両利きの経営だ。
破壊的イノベーションに立ち向かう

両利きの経営が求められる次のケースは、成熟市場で成功した事業が、「破壊的イノベーション」の挑戦を受けたときである。ハーバード・ビジネススクール教授のクレイトン・クリステンセンの著書に、『イノベーションのジレンマ』がある。1997年に出版されて以来、そのインパクトが広く知られるようになった。
挑戦を受けた企業は成熟事業で何とか競争をしながら(深化)、実験や試行錯誤で新しい技術やビジネスモデルを探求する(探索)必要がある。しかし、クリステンセンは、組織が探索と深化を同時に進めることは不可能なので、探索にあたるユニットを切り離して外に出す、つまり「スピンアウト」をしなければならないと考えた。
それに対して、本書の著者らは、探索と深化を分断すれば先細りになるという。そして、探索のユニットにも、既存の経営資源を最大限活用できるような仕組みが必要だと主張する。それこそが両利きの経営である。
破壊的イノベーションに飲み込まれた企業は数知れない。たとえば、アマゾンの挑戦に敗れて消えていった企業群がそれにあたる。
リードし、破壊せよ
本書の原題は、「Lead and Disrupt(リードし、破壊せよ)」である。これには、読者に対し「業界をリードするとともに破壊を仕掛ける側でいてほしい」という、著者らの希望が込められている。
それを体現している企業の一例がアマゾンだ。著者らは、1994年にインターネット書店からはじまったアマゾンの歴史を、3つのフェーズに分けた。失敗も含めてイノベーションをリストアップすると、その数は25項目にものぼる。
アマゾンは、既存の組織能力と市場を深化しつつ、新しい組織能力や市場を開拓してきた。それを支えているのは、「顧客満足へのこだわり」「低価格」「長期展望の重視」という一連の基本的価値観(コアバリュー)である。アマゾンのCEO、ジェフ・ベゾス氏は次のように語っている。「長期志向になれば、顧客の利益と株主利益は一致する。短期的に見れば、必ずしもそうではないのだ。(中略)発明には長期のアプローチが欠かせない。というのは、その途中で多くの失敗を経るからだ。」実際に、リーダーシップを発揮して、この方針を貫き続けている。
両利きの経営を成立させるには、組織を調整するリーダーの手腕が欠かせない。
両利きの経営を実践する
2つの組織ユニットをマネジメントする
それでは、成熟事業における「深化」とは、どのようなものなのか。トヨタの工場を思い浮かべてほしい。成功要因として重視されるのは、コストダウン、効率性と生産性の向上、漸進型イノベーションといったことだろう。効率性、コントロール、確実性に力点がおかれる。