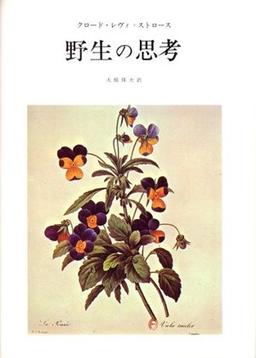【必読ポイント!】 「未開の思考」は存在しない
具体の科学

動植物の種類の名前は詳細にあるのに、「樹木」や「動物」といった抽象概念をもたない言語のことを、西洋社会は「未開人」の抽象的思考能力の欠如を証明するものとみなしてきた。
だが実際は「未開人のもの」とされた語の中にも、抽象的な言葉は数多く存在している。単に言語の切り取り方が、言語によって異なるというだけの話だ。その分野における用語の抽象度の違いを決めるのは、知的能力ではなく、その民族社会における関心の違いである。
そもそも「カシワ」や「ブナ」という言葉だって、「樹木」と同じく抽象概念である。ただその解像度が異なるというだけだ。むしろ樹木の種類を指す言葉が大量にあるとしたら、そちらのほうが概念的に豊かな言語ということになるのではないか。
概念が豊富ということは、現実のもつそれぞれの特性に対して、綿密に注意を払っていることの証だ。それが近代科学と同一レベルにあるかどうかはともかく、知的操作と観察方法という点においては、どちらも同じであることが言えるだろう。
また、西洋社会は「未開人は実用的な知識しか関心がない」と考えがちだが、これも実態は異なる。たとえばあるアメリカ大陸のインディアンたちは、食用にも社会的にもほぼ用いない爬虫類について、膨大な知識を持っている。それは知識欲のあらわれであり、このような例は世界中のありとあらゆるところで見られる。すなわち彼らは、「有用だから動植物に関する知識を蓄える」のではなく、「知識が先にあって、そこから有用・有益という判定を下す」のである。この点において、それぞれの文明間に大きな差異は存在しない。
呪術と科学は何が違うのか?
私たちが「未開思考」と呼ぶもの(=呪術)も近代科学も、自分たちの世界観の中に物事を位置づけ、異質なものを理解しようとする。呪術と科学の違いは、次のように表現できる。呪術はある因果関係を見いだしたらそれを拡張し、さまざま対象に当てはめようとするが、科学の場合はさまざまな場合に分けて、「ある条件下ではこれが成り立つ」という態度をとる。
このことからもわかるように、呪術と科学は完全に断裂したものではない。歴史を振り返れば、むしろ呪術のほうが科学より先に因果について感づいている。そういう意味で、呪術は科学に先立って生まれたものともいえる。
かといって、呪術が単なる科学の出来損ないというわけではない。呪術を科学や技術の発達の前段階とみなすだけだと、呪術的思考についての理解を損なってしまう。呪術的思考は、それ自体で諸要素をまとめた一つの体系を構成しており、したがって科学の体系からは独立したものである。両者は対立するものではなく、あくまで認識の形態が異なるだけなのだ。
たしかに科学のほうが、有効に働く場面は多い。だがそれは、根本的な知的操作の性質が異なるからではなく、適用される現象のタイプが異なるからである。
ブリコラージュと野生の思考

近代科学の誕生はわずか数世紀前とされている。しかし科学的な態度の起源は、新石器時代まで遡ることができる。この時期に、土器や織布、農耕、動物の家畜化など、文明を形成するうえで重要な技術が生まれたからだ。
技術の誕生にはいずれも、何世紀にもわたる観察と仮説、およびそれらにもとづく実験と検証が不可欠である。そこにあるのは科学的な精神、根強い好奇心、知る喜びにあふれた知識欲にほかならない。こうした「具体の科学」は、近代科学と同じく学問的であり、依然としていまの文明の基盤をなしている。
このような科学のあり方は、いまの私たちの文明の中にも見いだせる。それは「ブリコラージュ」(器用仕事)と呼びうるものだ。ブリコラージュは、