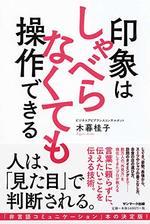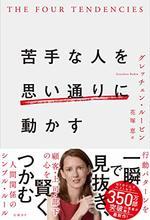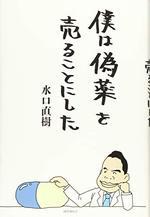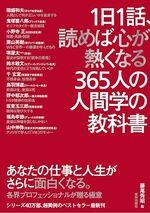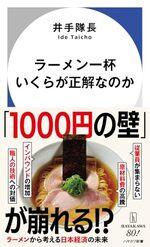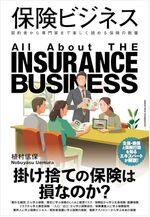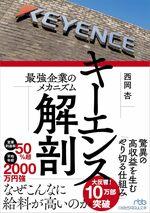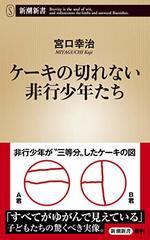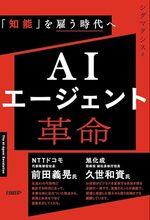【必読ポイント!】日本社会の3つの生き方
「大企業型」と「地元型」

現代日本社会での生き方は「大企業型」「地元型」「残余型」の3つの型に分けられる。「大企業型」とは、大学を出て大企業や官庁に就職し、「正社員・終身雇用」の人生を送る人たちとその家族の生き方だ。
「地元型」は、地元から離れない生き方である。地元の中学や高校を卒業し、農業、自営業、地方公務員、建設業、地場産業など、その地域に根差した仕事に就く。
「地元型」の収入は「大企業型」よりも少なくなりがちだが、実家に住むなら住宅ローンはないし、近所からの「おすそ分け」が多い分、支出も少ない。
さらに「地元型」は、商店会、自治会などの結びつきがあるため、政治力がある。行政が地域住民としてまず念頭に置くのは「地元型」の人たちであり、政治的な要求も届きやすい。
一方、「大企業型」は地域に足場を失いがちだ。地元を離れて暮らしていることが多いだけでなく、転勤があればひとつの地域に長く住むことはない。定年後の生き方に迷う問題や、近隣を頼れないことからくる育児の問題もある。ローンで家を買うなど支出も多い。日中在宅していないので、政治家もあまり呼びかけの対象にしない。
「地元型」と「大企業型」は、それぞれ生きる状況が大きく異なり、違った不満を持っている。だが、「日本」を論じるとき、念頭に置かれがちなのは「大企業型」だ。それは、論じる人の多くが大都市のメディア関係者だからだ。
その感覚でいえば、「日本人」は満員電車で通勤し、保育園不足に悩んでいることになる。しかし実際には、そうした人は「日本人」のごく一部にすぎない。
「残余型」
日本の社会保障制度は、「大企業型」と「地元型」を前提につくられている。
その一方で、現代の日本社会には「長期雇用はされていないが、地域に足場があるわけでもない」人々が増えつつある。本書では、そうした人々を「残余型」と呼ぶ。
都市部の非正規労働者がその象徴だ。所得は低く、地域につながりもなく、持ち家がなく、年金は少ない。「大企業型」と「地元型」のマイナス面を集めたようなタイプである。
「残余型」は、必ずしも所得が低いわけではなく、典型的な生き方もない。共通しているのは、政治的な声をあげるルートがない点だ。「大企業型」のように労働組合に所属しているわけでもなければ、「地元型」のように町内会や業界団体に入っているわけでもない。
現代日本社会は、「大企業型」「地元型」「残余型」の3つのタイプで構成されている。厳密な割合を出すことはできないが、「地元型」が36%、「大企業型」が26%、「残余型」が38%程度と推計される。
日本社会の「しくみ」と欧米社会の「しくみ」
日本は「社員の平等」欧米は「職務の平等」

日本での格差は「大企業か中小企業か」、つまり「どの会社か」によって決まる。一方、ヨーロッパやアメリカなどでは「ホワイトカラーかブルーカラーか」、つまり「どの職務か」が強く意識される。
欧米などの企業は三層構造で説明される。上から「目標を立てて命令する仕事」である「上級職員」、「命じられた通りに事務をする仕事」である「下級職員」、そして「命じられた通りに体を動かす仕事」である「現場労働者」だ。