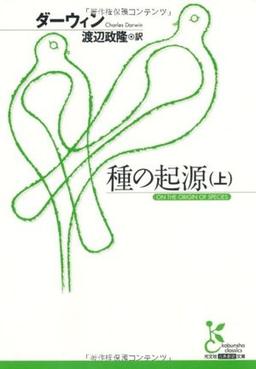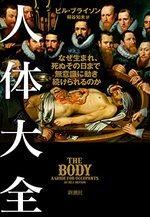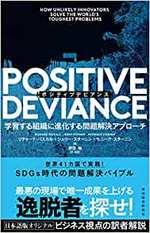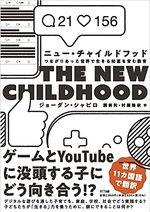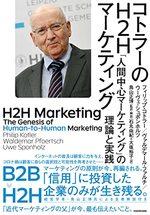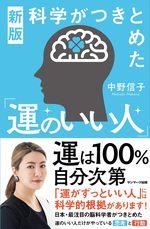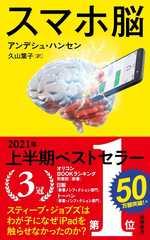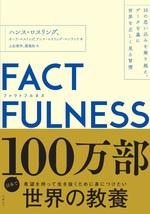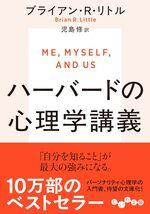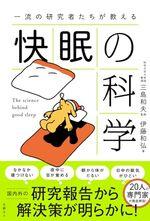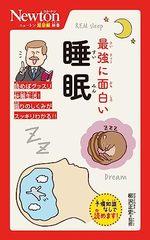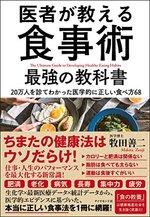変異とは何か
飼育栽培下での変異
長年飼育栽培されてきた植物や動物のほうが、野生状態にあるものより、一般に変異がはるかに多い。それは飼育栽培下のほうが環境が多様である上に、環境自体が異質だからだ。
では、成長過程のどの段階に、変異を生じさせる原因があるのか。一つは、親の生殖因子が受精前に影響を受けるのではないか、ということだ。飼育下でまったく繁殖しなくなる植物や動物もある。
また習性にも変異を起こす大きな影響力がある。たとえばカモとアヒルを比べた場合、全骨格に対する翼の骨の重量比率は、家禽であるアヒルのほうが小さい。原種にあたるカモに比べると、アヒルはほとんど翼を使わないからだ。
変異には謎めいた相関作用が見られる。脚の長い動物は、ほぼ必ず頭も長い。眼の青いネコは、例外なく耳が聞こえない。
飼いバトの研究から気づいたこと

古い歴史をもつ家畜や作物の大半は、その原種が一種なのか複数種なのか、明確な結論は出ない。ただ、アヒルと飼いウサギは品種ごとに形態がかなり異なっているが、それぞれ一種類の野生のカモとアナウサギの子孫であることは疑いない。
ダーウィンはこの研究の最善の方法として、飼いバトに的を絞った。頭部にみごとな肉だれのあるものや、長くて頑丈なくちばしと大きな足を持つものもいれば、翼と尾の長いものや尾が著しく短いものもいる。野生の鳥だとしたら、20種に分けてしまうところだ。
しかし他のナチュラリスト同様、ダーウィンもすべての品種はカワラバトただ一種の子孫であると考えている。カワラバトがヨーロッパとインドで飼い慣らされていて、習性についても形態の多くの特徴においてもすべての品種と一致していることが、その理由の一つだ。
「選抜」の原理とその「威力」
飼育栽培品種が一つあるいは複数の近縁種から作り出されるのは、そこに「選抜」という原理が働いているからだ。
人間は自分のために有用な品種を作り上げてきた。ただ、「選抜」という原理を使う「改良」は、単に異なる品種をかけ合わせればよいわけではなく、熟練者にしか見抜けないようなごく小さな差異を何代もかけて一つの方向に蓄積させた結果、生みだされるものである。
人間による「選抜」という累積的な作用は、生活条件などの「変化」よりも「威力」としてはるかに優勢だ。
自然条件下での変異
自然条件下でも同じだ。ただし、差異が一つの種のなかの個体差なのか、変種であるのかの区別は曖昧で、憶測が入り込む余地も多い。
しかし個体差は、わずかな変種を生む最初の一歩になりうる。変種がその原種からさらに異なる状態へと移行する過程は、自然淘汰が働いて、形態上の差異がある一定の方向へと蓄積していくことによるものである。種とはよく似た個体の集まりに対して便宜的な呼び名であり、変種という呼び名と本質的には違わない。
【必読ポイント!】 生存闘争と自然淘汰のメカニズム
有用な個体差が子孫に受け継がれる
個体のわずかな変異がその種にとってほんの少しでも有利なものなら、その個体の生存を助け、変異した性質が子孫に受け継がれるだろう。そうした個体は生存率も高まるはずだ。多数の個体が生まれるなかで、生き残れるのは少数だからである。わずかな変異でもそれが有用ならば保存されるというこの原理を、自然淘汰の原理と呼ぶ。