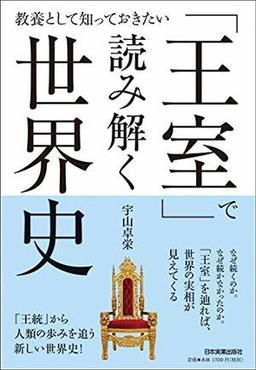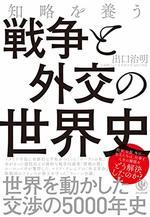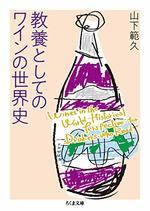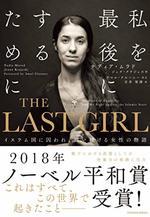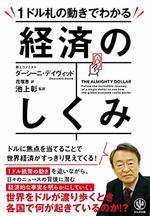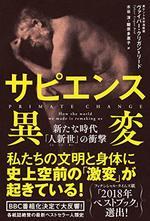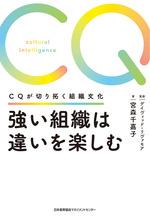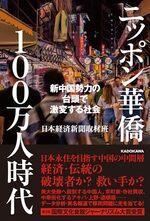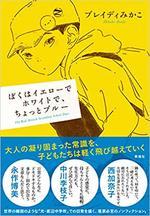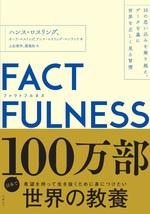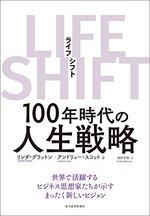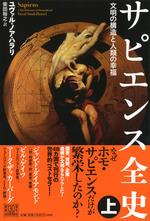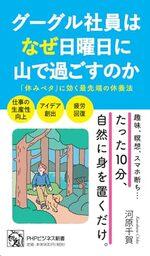【必読ポイント!】 万世一系の日本の皇室
王室とは何か

王とは血筋そのものだ。王が王であるためには、王の血を引くことが原則となる。そして王の血統は、王の自己満足ではなく民衆に必要なものでもある。もし誰もが王になれるなら、戦争の絶えない世の中になる。王の血統は秩序と等しい。
「王室の安泰=秩序維持の根幹」という原則を最も理解していたのは、日本人である。日本には、万世一系の天皇家がある。系譜を約1500年辿ることのできる王室で、王統の一貫性を有するのは、世界中で日本だけだ。
日本では源平の時代から数百年にわたり、武家が政権を握ってきた。だが、いかなる武人政権も天皇の地位を侵すことはなかった。武人は天皇の血統が神聖不可侵であることを理解し、天皇から委託された政権を預かることを前提として政治を司っていた。日本では、この「正統主義」を政治の原則とすることで、国家の安定を維持できたのである。
では、王の血統が失われるとどうなるか。歴史上、最も正統主義がないがしろにされてきたのは中国だ。王の血統は顧みられず、農民や異民族でも、力さえあれば王朝を興すことができた。その端的な例は、14世紀に明王国を建立した朱元璋だ。彼は貧農から身を起こして天下を取った。しかし、その背景から疑心暗鬼に陥り、人心の荒廃を招くこととなった。
中国では王朝が頻繁に変わったせいで、人民に国という意識が根付かなかった。国の意識がないと、公共意識も育たない。自分さえよければよいという考えは、現代まで綿々と続いているのだ。
「男系天皇」に秘められた日本の知恵
日本の『皇室典範』第一条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とある。「皇位継承権を男系男子の皇族に限るのは、女性差別だ」という批判があったが、それは見当違いだ。そもそも『皇室典範』は、女性差別を意図するものではない。
まず、「男系」とは、「皇族の父親と一般女性」の間に生まれたという意味であり、性別は問わない。我が国にはかつて「女性天皇」が8名いたが、いずれも「男系天皇」である。歴史的に「女系天皇」を認めたことはない。
ではなぜ、男系継承の維持が必要なのか。もし、女性天皇が民間男性と結婚したら、生まれた子は民間男性の家系の子になる。その子が皇位継承すれば、その民間男性の家系の新王朝が興ることになる。つまり、女系天皇を認めるということは、民間人に皇室が乗っ取られることを意味する。野心的な男が皇族に近づき、自分の子を天皇にして自らの王朝をつくることも可能なのだ。女系天皇を歴史的に認めてこなかったのは、国を守るための防御策なのである。
一方ヨーロッパでは、このような規定がなかったため、女系王の即位によって国が乗っ取られた例が多数ある。その有名な例がスペインだ。スペイン王国の王女ファナは、ハプスブルク家の皇子フィリップと結婚し、カール5世を産む。スペイン王国には男子の世継ぎがいなかったため、カール5世はスペイン王位を継承した。こうして、スペイン王国は合法的にハプスブルク家に乗っ取られたのである。
王と皇帝の違い

では皇帝(エンペラー)と王(キング)はどう違うのか。ローマ帝国の例をもとに説明しよう。
ヨーロッパでは、皇帝はローマ帝国の「カエサルの後継者」という意味を持つ。ローマ帝国は西暦395年、東西に分裂し、西ローマ皇帝と東ローマ皇帝が並び立つようになった。しかし、西ローマ帝国は476年に滅亡。その後300年以上の空白の時期を経て、800年、フランク族のカール(大帝)が西ローマ皇帝の座に就く。西の皇帝位を962年に引き継いだのは、カールの血を引くオットー1世。彼は神聖ローマ帝国を樹立した。これは15世紀に、オーストリア貴族出身のハプスブルク家に引き継がれていく。
一方、現在のイスタンブルに首都が置かれた東ローマ帝国は、1453年にオスマン帝国に滅ぼされるまで、約1000年にわたり存続した。1480年、ロシア貴族のイヴァン3世が東ローマ皇帝位の後継者に名乗り出る。子のイヴァン4世の時代に帝位継承を認められ、以降、ロシア人が皇帝を引き継いでいく。
このように、王は血統・血脈の正当性を前提とするのに対し、ヨーロッパの皇帝は基本的に概念的・政治的なものと言える。
ところで、大英帝国(British Empire)には皇帝がいないのに、なぜ帝国と呼ばれるのか。帝国は「複数の地域や民族を含む広大な地域を支配する国家」を指し、国家の形態を表す。したがって、イギリスのように、君主が皇帝である必要はないのだ。
ヨーロッパの王室
国王を処刑したイギリスとフランス

歴史上、民衆の意思により国王が処刑された例が2つある。イギリス国王チャールズ1世とフランス国王ルイ16世だ。
両国とも、革命後に王制が復活している。復活後、イギリスの王制は存続中だが、フランスでは再び廃止され、共和制のまま今に至る。両国の違いは何なのか。